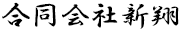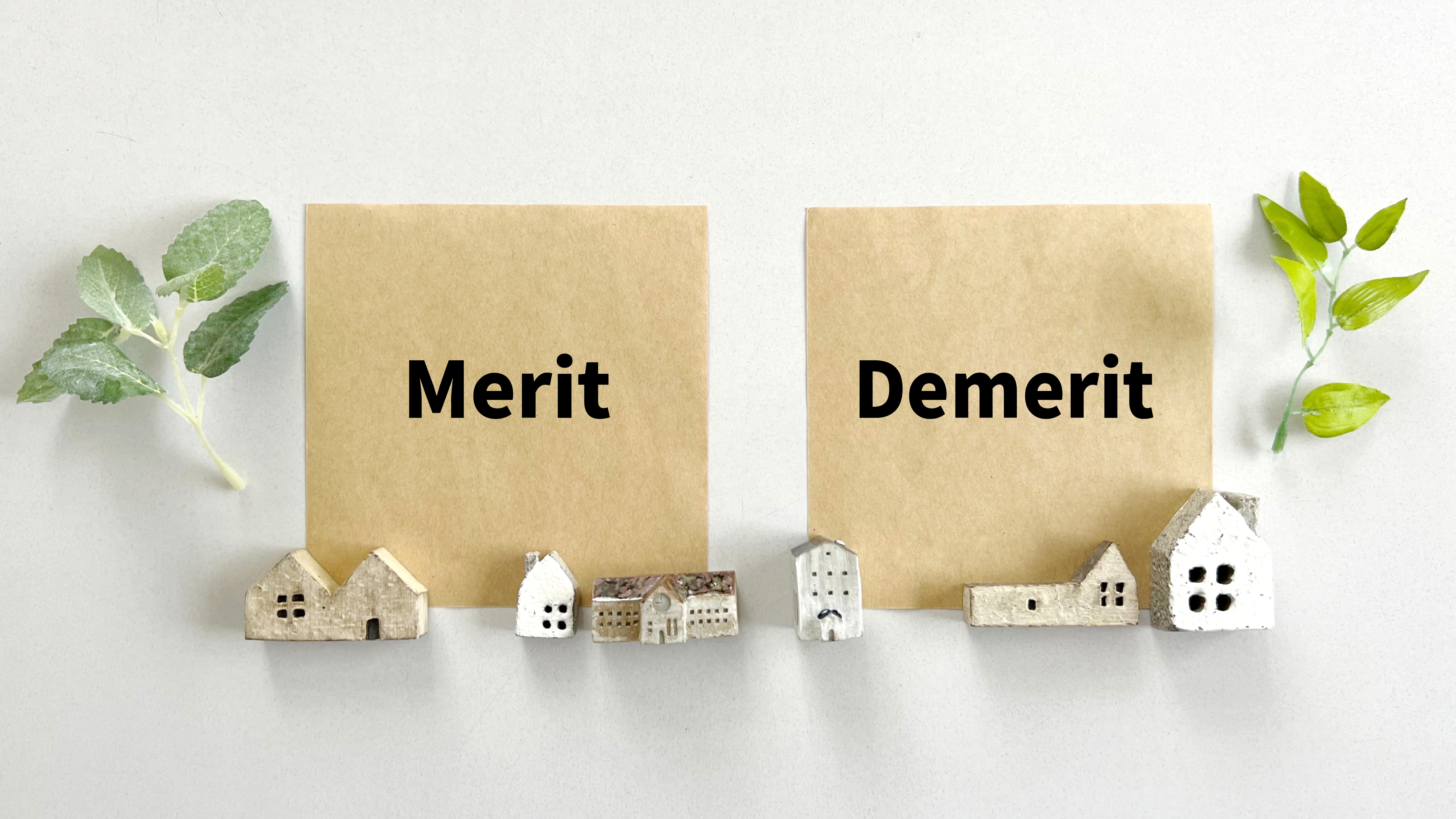相続に関する義務化について知っておくべきことは?負動産の処分方法も解説

これまで相続は権利として扱われてきましたが、近年の法改正により、相続人には一定の義務が課せられるようになっています。
特に不動産の相続においては、空き家や使わない土地などの「負動産」を引き継ぐことで、予想以上の負担を背負うケースが増えています。この記事では、相続に関して義務化された内容と、相続した不動産で困った時の解決策についてわかりやすく解説します。
目次
【「相続に関する義務化」とは何か】
複数の法改正により、相続人が一定の義務を負うようになりました。
その義務の内容についてご紹介します。
<相続登記の義務化>
2024年4月から、相続登記が義務化されました。これは相続によって不動産を取得した人が、相続を知った日から3年以内に登記申請を行わなければならないという制度です。
正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。この制度は、所有者不明土地の発生を防ぐために導入されました。
登記を行わないと過料の対象となるだけでなく、将来的に不動産の売却や活用が困難になる可能性があります。
<相続財産管理の義務>
相続人は、相続財産を相続放棄するまでの間、適切に管理する法的義務を負います。これは、債権者や他の利害関係者に損害を与えないよう、財産の状態を維持しながら慎重に取り扱う責任を意味します。
特に不動産の場合は、建物の安全性を確保し、敷地を適切に維持することに加え、近隣への配慮も重要です。倒壊や管理不備によって周囲に迷惑をかけることのないよう、継続的な維持管理が求められます。
【相続に関する義務化が生まれた背景】
相続に関する義務化が生まれた背景には、社会の深刻な問題があります。
<所有者不明土地問題の深刻化>
日本全国で所有者が分からない土地が急激に増加しています。これらの土地は適切な管理がされず、公共事業の妨げになったり、周辺環境の悪化を招いたりしています。
国土交通省の調査によると、所有者不明土地の面積は九州本島の面積を上回るとされており、この問題を解決するために相続登記の義務化が導入されたのです。
<空き家問題の拡大>
高齢化と人口減少により、相続しても使わない空き家が全国で増え続けています。これらの空き家は放置されることで、防犯上の問題や景観の悪化、近隣への迷惑など様々な社会問題を引き起こしています。
そのため、相続人が責任を持って不動産を管理することが法的に求められるようになりました。
【負動産問題とは】
相続に関する義務化が進む中で注目されているのが「負動産」の問題です。
<負動産の定義>
負動産とは、所有していることで利益よりも負担の方が大きくなってしまう不動産のことです。固定資産税や管理費、修繕費などの維持コストが継続的にかかる一方で、活用や売却が困難な状態にある不動産を指します。
典型的な負動産には、地方の空き家、原野商法で購入された土地、リゾートマンション、再建築不可物件、共有名義の不動産などがあります。
<負動産を相続するリスク>
負動産を相続すると、毎年の固定資産税の支払い義務が発生します。さらに建物がある場合は、台風や地震による損壊リスク、不法侵入や放火などの防犯リスクも抱えることになります。
また、近隣に迷惑をかけた場合は損害賠償責任を問われる可能性もあり、相続人にとって大きな精神的・経済的負担となります。
【相続した不動産で困った時の対処法】
負動産を相続してしまった場合に行うべきことについてご紹介します。
<現状を把握する>
相続した不動産がどのような状態にあるのか、正確に把握することが重要です。登記簿謄本や固定資産税の納税通知書を確認し、所有権の状況や年間の維持費用を整理しましょう。
また、実際に現地を確認して建物の損傷状況や周辺環境も調査することで、今後の対策を検討する材料が揃います。
<売却可能性の検討>
一般的な不動産会社では取り扱いが難しい物件でも、専門の業者であれば買取りが可能な場合があります。立地や条件によっては、思っていたより良い条件で売却できることもあります。
複数の業者に査定を依頼し、売却の可能性を検討してみることをおすすめします。
【相続土地国庫帰属制度の活用】
2023年4月から、相続土地国庫帰属制度が始まりました。
この章では、制度の内容や手続き方法をご紹介します。
<制度の概要>
この制度は、相続した土地を国に引き取ってもらうことができる制度です。一定の要件を満たした土地について、相続人が申請することで国庫に帰属させることが可能になりました。
<制度利用の条件と手続き>
制度を利用するには、土地が一定の条件を満たしている必要があります。具体的には、建物がないこと、担保権が設定されていないこと、境界が明確であることなどが求められます。
また、申請時には審査手数料(土地一筆当たり14,000円)と、承認された場合の負担金(10年分の土地管理費相当額)の支払いが必要です。
【専門業者による不動産引き取りサービス】
国庫帰属制度の要件を満たさない不動産や、より柔軟な解決を求める場合は、専門業者の引き取りサービスを検討することができます。
<引き取りサービスのメリット>
専門業者による引き取りサービスは、建物付きの土地や複雑な権利関係の不動産でも対応可能な場合が多いという特徴があります。また、手続きも比較的簡単で、迅速な解決が期待できます。
国庫帰属制度と異なり、土地の種類や状態による制限が少なく、相続で取得した空き家や空き地はもちろん、原野商法で購入してしまった使い道のない土地、維持費の負担が大きいリゾートマンション、共有名義で他の所有者と連絡が取れない不動産なども対象となることがあります。遠方にあって管理が困難な不動産や、長年放置されて荒れ果てた土地、山林や別荘地、再建築不可物件など、一般的な不動産会社では取り扱いが困難な物件でも、専門的な知識と経験を持つ業者であれば適切に対応してくれます。
<安心できる業者の選び方>
引き取りサービスを利用する際は、信頼できる業者を選ぶことが重要です。透明性のある査定プロセス、明確な手続き説明、適切な契約書の作成など、安心して任せられる業者を選びましょう。
優良な業者の特徴として、まず無料での相談や査定を行っていることが挙げられます。所有者の立場に立って親身に相談に乗り、無理な契約を迫ることなく、丁寧に状況を聞いてくれる業者が信頼できます。
また、査定においては公正で透明性のある評価を行い、なぜその価格になるのかを分かりやすく説明してくれることも重要なポイントです。手続きについても、複雑な法的手続きを代行してくれ、所有者の負担を最小限に抑えてくれる業者を選ぶべきです。
<相談から解決までの流れ>
専門業者への相談から実際の引き取りまでの流れを理解しておくことで、安心して手続きを進めることができます。
・初期相談
電話やメール、専用の相談フォームを通じて物件の概要や困っている内容を伝えます。多くの業者では、この段階での相談は無料で行っています。
・具体的な査定
物件の資料や現地の状況を確認し、引き取りの可否や条件について検討が行われます。この際、登記簿謄本や固定資産税の納税通知書、物件の写真などが必要になる場合があります。
・契約内容の確認
査定結果が出た後は、引き取り条件の説明と契約内容の確認が行われます。費用や手続きの流れ、必要書類などについて詳しく説明を受け、納得できれば正式な契約に進みます。
・法的手続き
所有権の移転登記などの法的手続きが完了すれば、不動産の引き取りが完了し、以後の管理責任や費用負担から解放されます。
【早期解決が重要!負動産を放置した場合のリスク】
相続した負動産の問題は、時間が経つほど解決が困難になる傾向があります。放置した場合のリスクを知っておきましょう。
<放置することのリスク>
負動産を放置していると、様々なリスクが拡大していきます。建物がある場合は経年劣化により倒壊の危険性が高まり、近隣への被害が発生すれば多額の損害賠償責任を負う可能性があります。
また、空き家は不法侵入や放火などの犯罪に利用されやすく、地域の治安悪化の原因となることもあります。雑草の繁茂や害虫の発生により、近隣住民からの苦情が寄せられることも珍しくありません。
<維持費用の継続的な負担>
負動産を所有している限り、固定資産税の支払い義務は継続します。また、最低限の管理を怠ると行政から改善命令が出される場合もあり、対応しなければ行政代執行により強制的に解体され、その費用を請求される可能性もあります。
特に空き家の場合、特定空家等に指定されると固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、税負担が大幅に増加することもあります。
<家族への負担>
負動産の問題を解決せずに放置していると、最終的にはその負担が家族や次世代に引き継がれることになります。相続義務化により、相続人は法的な責任を負うことが明確になったため、問題の先送りはより深刻な結果を招く可能性があります。
自分の代で適切に処理することで、家族に迷惑をかけることなく、安心して暮らしていくことができます。
【まとめ】
相続関連の義務化が進んだことにより、相続人の責任は以前より重くなりました。特に不動産の相続では、登記義務と管理責任を適切に果たすことが法的に求められています。
負動産を相続してしまった場合でも、相続土地国庫帰属制度や専門業者の引き取りサービスなど、様々な解決策が用意されています。一人で悩まず、まずは専門家に相談することで、最適な解決方法を見つけることができるでしょう。
大切なのは、問題を先延ばしにせず、早めに適切な対処を行うことです。相続した不動産でお困りの際は、遠慮なく専門家に相談することをおすすめします。